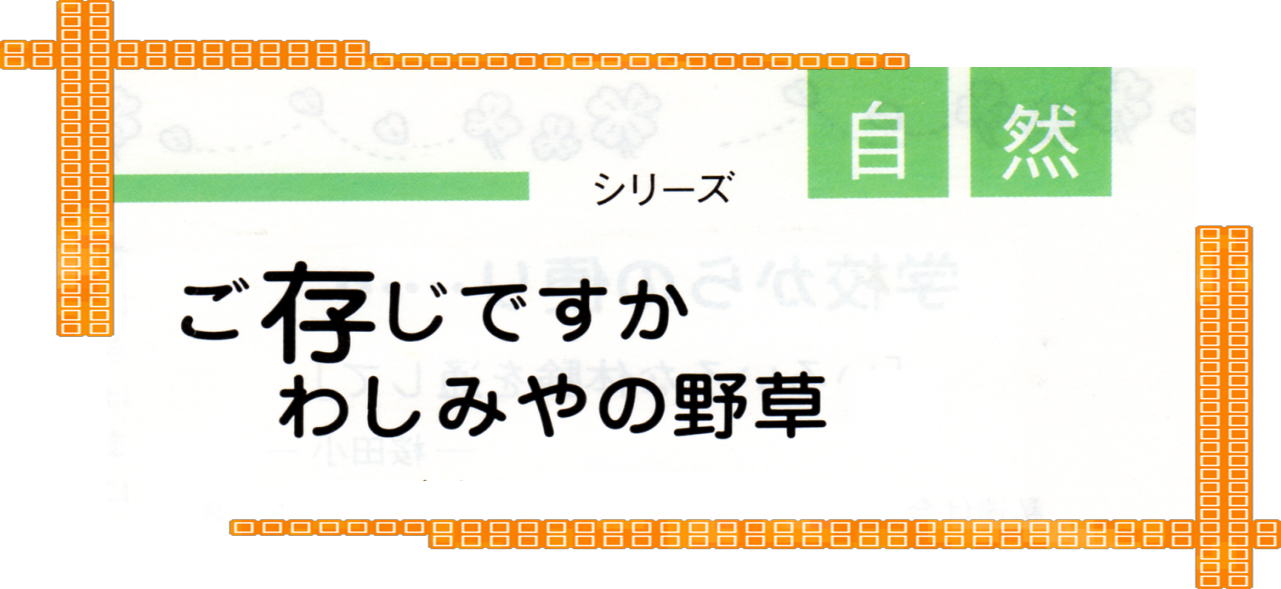
広報わしみや No.333~338
平成10年4月~平成10年9月
 ヤブニンジンは、山地の藪(やぶ)や林のへりなど日陰にはえる多年草で、茎は直立して枝分かれします。葉は長い柄があり、二~三回羽状(うじょう)に裂(さ)け、切れ込みが深く、やや光沢があります。葉の両面に毛があり裏側は白っぼく見えます。地上部分がニンジンに似ているので、この名があります。
ヤブニンジンは、山地の藪(やぶ)や林のへりなど日陰にはえる多年草で、茎は直立して枝分かれします。葉は長い柄があり、二~三回羽状(うじょう)に裂(さ)け、切れ込みが深く、やや光沢があります。葉の両面に毛があり裏側は白っぼく見えます。地上部分がニンジンに似ているので、この名があります。花は白色で小さく、花期は四~五月です。花序(かじょ)はまず大きな枝三~六個を分け、それぞれの先に五~十個の花をつけます。
果実は先が太く、長さ約二センチであらい毛が密生し、熟すと人の体にくっつくのでナガジラミともよばれます。根茎(こんけい)(根のように見える地下茎) は「和藁本(わこうほん)」とよばれ、鎮痛(ちんつう)、鎮痙(ちんけい)作用があります。
似た種類のオヤブジラミは、道ばたや草原、土手など
 にはえる二年草で、花期は四~五月ですが、果実は長さ四~六ミリで、花とともに淡紫色をおびます。
にはえる二年草で、花期は四~五月ですが、果実は長さ四~六ミリで、花とともに淡紫色をおびます。ヤブジラミも似ている種類ですが、花期が五~七月と遅く、花は白色で、果実は約三ミリと小さいので見分けられます。
どちらも果実にとげがあり人の体について運ばれるので藪(やぶ)の虱(しらみ)と呼ばれます。
【写真左上は栗原地内、右下は八甫中川堤防にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 スズメノエンドウは、野原や道ばた、あき地、田畑のまわりなどに生育します。茎はつる状にのび、葉は十二~十六枚の小葉からなり、葉先は三~五本の巻きひげとなって、ものにからみます。
スズメノエンドウは、野原や道ばた、あき地、田畑のまわりなどに生育します。茎はつる状にのび、葉は十二~十六枚の小葉からなり、葉先は三~五本の巻きひげとなって、ものにからみます。花期は四~五月で、葉のつけ根から出る枝の先に三~七個の花をつけます。花の長さは三~四ミリでごく淡い紫色をしています。豆果(とうか)(果実) には、こまかい毛が密生し、中に種子が二個人っています。
カラスノエンドウ (烏野豌豆~わしみやの野草25参照)に対して葉や花が小形であることからスズメの名がついています。
スズメノエンドウによく似て、同じような所にはえるカス
 マグサは、次の点で見分けられます。
マグサは、次の点で見分けられます。①豆果は無毛で三~六個の種子がある。
②花は長い柄の先に一~三個つき、長さ五ミリで淡紅紫色。
③葉や茎はスズメノエンドウよりも毛が少ない。
④小葉は八~十二枚で少ない。
⑤葉の色は明るい緑色で、小葉の先は丸みがある。
カスマグサの名は、その姿がカラスノエンドウとスズメノエンドウの両者の中間型を示しているので、その頭文字をとって、カとスの間という意味でカスマグサとなりました。
【写真左上、右下ともに上内地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 カモジグサは「髢草(かもじぐさ)」 の意味で、女の子がこの草の若い葉をよって束ね、雛人形の髢(かもじ)(髪を結うとき、添えて用いる髪)を作って遊んだことに由来すると、牧野富太郎博士は説明しています。
カモジグサは「髢草(かもじぐさ)」 の意味で、女の子がこの草の若い葉をよって束ね、雛人形の髢(かもじ)(髪を結うとき、添えて用いる髪)を作って遊んだことに由来すると、牧野富太郎博士は説明しています。草原や道ばたに多く見られる多年草で、茎は根ぎわから束のように枝を出し、株立ちのようになります。葉は多少白っぼい緑色で長さ約二十センチ、線形でコムギの葉に似ています。
花期は五~七月で、花穂は長さ二十センチ前後あり、二十~三十個の小穂が二列に並んで、穂は弓なりに垂れます。 小穂は長さ十五~二十五ミリあり、ふつう緑白色で芒(のぎ)が紫色に染まり、五十~十の小花からなります。
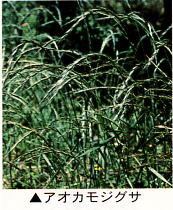
小花は、それぞれ外側の穎(えい)に直立する芒(のぎ)があります。穎は無毛で、内側と外側の穎が同じ長さです。
似た種類のアオカモジグサも、カモジグサと同じように花期は五~七月です。農耕地や市街地の道ばた、草地などにふつうに見られる多年草ですが、カモジグサとは、小穂に毛があることと、内側の穎が外側の穎より短いことで区別できます。小花をひとつ取り出して内側をルーペで見るとよくわかります。
【写真左上は東大輪、右下は桜田三丁目沼井公園にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 ヤブミョウガは漢字で藪茗荷と書き、ミョウガ (ショウガ科) に似ていて、やぶのなかに生えるところから名づけられました。
ヤブミョウガは漢字で藪茗荷と書き、ミョウガ (ショウガ科) に似ていて、やぶのなかに生えるところから名づけられました。太い根茎(こんけい)(地中を長く横にはい、根のように見える茎、節があるので根と区別できる)があって、茎は高さ五十~一〇〇センチになり、葉面とともに目だってざらつきます。
葉は大きく、二列に並び、基部はさやとなって茎をつつみます。たくさんの白い花が五重の塔のように数段に分かれて咲きます。同じ株に両性花(りょうせいか)(一つの花におしべとめしべがある花) と雄花がつき、両性花ではめしべがおしべより長く、雄花ではめしべが退化して見えにくくなっています。
花期は七~九月です。花は直径約八ミリで、がく片三、花弁(かべん)三
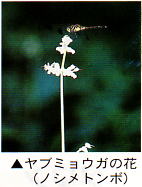 、おしべ六、めしべ一よりなり、がく片も花弁も白色です。花は一日でしぼみますが、がくは厚くて、花後まで残り果実を抱きます。
、おしべ六、めしべ一よりなり、がく片も花弁も白色です。花は一日でしぼみますが、がくは厚くて、花後まで残り果実を抱きます。果実は球形で、直径約六ミリ、藍青色(らんせいしょく)に熟し、乾いても裂(さ)けません。種子は直径約二ミリです。
花のないときは、ミョウガと間違いやすいですが、ミョウガは茎も葉もなめらかで、もむと香りがあるので区別ができます。
※写真右下ヤブミョウガの花に止まっているのはノシメトンボ(慰斗目蜻蛉) です。
【写真左上、右下ともに鷲宮神社の林下にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 クサネムは湿地にはえ、川のほとりや田の畔、休耕田などで見られます。
クサネムは湿地にはえ、川のほとりや田の畔、休耕田などで見られます。茎は無毛で高さ五十~一〇〇センチになり、淡緑色で上部は中空です。葉は二十~三十対の小さな小葉が密接して並び、下面は粉を付けたような白色をしています。ネムノキに似た多数の小葉をつけるところからクサネムの名があります。ネムノキは夕方にならないと葉が閉じませんが、クサネムの方は触っただけでゆっくりと葉が閉じていきます。夜間や雨の日は葉面を中側に折りたたんで眠ります。
学名アエスキノメネ インディカのアユスキノメネは、ギリシア語で「恥ずかしがった」の意味で、夕方、葉が閉じて垂(た)れる様子を、草が恥ずかしがっていると擬人的(ぎじんてき)に見た、リンネが命名したものです。
花は長さ一センチで黄色からうす黄色の蝶形花で、七月から十月に咲きます。
 果実は無毛で長さ三~五センチ、幅五ミリで六~八節があり、熟すと節ごとに離れて落ち、一節ごとに一種子があります。果皮がコルク質で軽いので水に浮いて流れ散布されます。
果実は無毛で長さ三~五センチ、幅五ミリで六~八節があり、熟すと節ごとに離れて落ち、一節ごとに一種子があります。果皮がコルク質で軽いので水に浮いて流れ散布されます。似た種類のカワラケツメイは平地の草原にはえる一年草です。茎は堅く上部に毛があり、中空ではなく、葉はクサネムより緑が濃く、小葉の先がとがっています。果実はへん平、長さ三~四センチで短い毛が密生し、熟して二片に裂けるのでクサネムと区別できます。
【写真左上、右下ともに宝泉寺池付近にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 ゴキヅルは、低地の水辺や湿地にはえる蔓(つる)性の一年草です。茎は細くて、茎の変形した巻きひげで他の草にからまりながら伸び、約二メートルになります。巻きひげの先は二つになることもあります。
ゴキヅルは、低地の水辺や湿地にはえる蔓(つる)性の一年草です。茎は細くて、茎の変形した巻きひげで他の草にからまりながら伸び、約二メートルになります。巻きひげの先は二つになることもあります。葉はふつう長い三角形で、ときに三~五裂(れつ)するものがあります。切れ込みの深さによって、ハンモミジゴキヅル、モミジバゴキヅル、ツタバゴキヅルと区別されることがありますが、これは皆同じ種のなかの変異です。
花期は八~十一月で、花は黄緑色、径七ミリ、がくも花冠(かかん)(花弁の集まり)もともに深く五裂し、裂片(れっぺん)はほぼ同じ形で交互に並びます。
長さ一・五センチほどの卵形の果実は、表面にとげのような突起があり、熟すると横に割れ、ふたがとれて中から二個の大きな種子が顔を出します。

ゴキヅルの名は、果実が上下に裂(さ)ける様子がちょうど椀(わん)の蓋(ふた)がとれるようであることから、蓋つき椀である御器(ごき)(合器(ごうき)) にたとえたといわれます。
似た種類のスズメウリ(わしみやの野草-54-平成六年九月号参照)も水辺を好んではえる一年生のつる草です。ゴキヅルもスズメウリも、以前は農村のやっかいな雑草でしたが、河川改修や除草剤などの影響で、現在ではむしろ珍しい植物になりつつあります。ちなみに、埼玉県植物誌(一九九八年版) によれば、県内のゴキヅルの分布は十三市町村となつています。
【写真左上、右下ともに宝泉寺池付近にて撮影】 写真と文 長須 房次郎