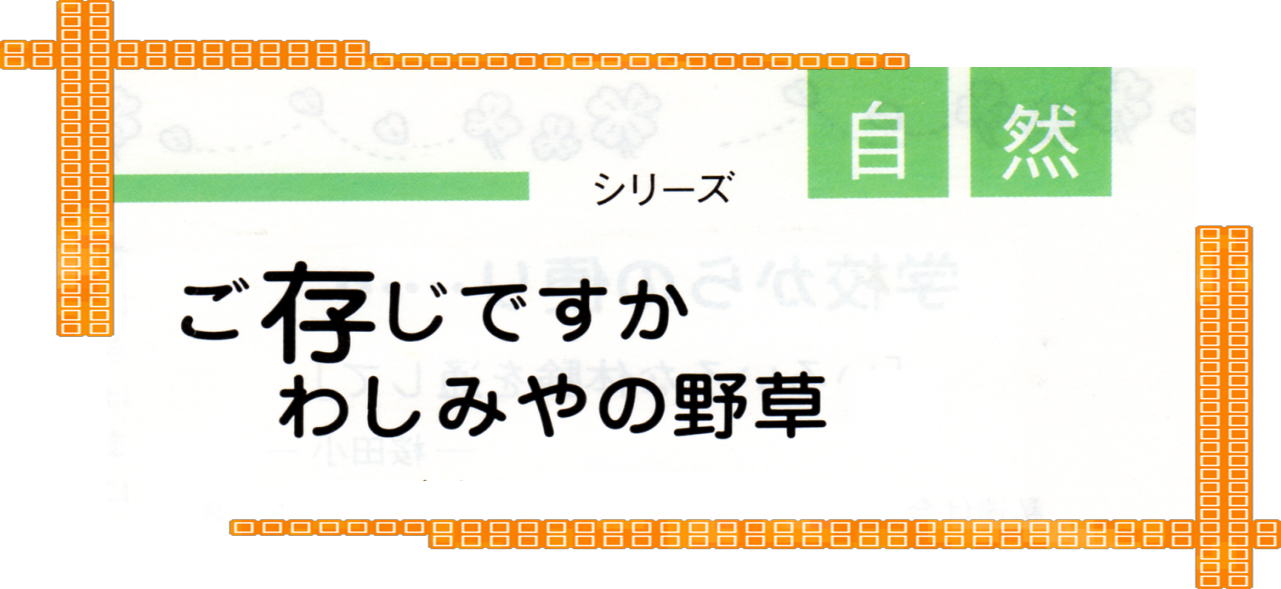 広報わしみや No.243~248
広報わしみや No.243~248平成2年10月~平成3年3月

「枸杞(くこ)酒を飲めば元気がでる」というキャッチフレーズで、いちじブームをおこして注目された植物。
つる性の小低木で、若い枝は長く伸び、先端は垂れ、小枝がとげになっていることもあります。道ばた、堤防の上などに生え、夏から秋にかけて、釣り鐘状をしたうす紫色で小さい花を葉のつけねのところにつけるが見栄えはしません。
果実はだ円形の液果(えきか)で、秋に熟すると鮮やかな紅色となり美しく、観賞用として生け垣にも使われます。
果実を酒や焼酎(しょうちゅう)につけたものが枸杞酒で、からだの弱い人の強壮薬とされ、中国では古くから薬酒として飲用されています。

道ばたや畑地、堤防など日当たりのよいところに生える一年生の草本。
小花は二個で花弁がない。果実は総包につつまれたままで、鉤状のとげで動物について散らばる。このように実が動物について散らばる植物には、イノコズチ、センダングサ、アメリカセンダングサ、ヌスビトハギなどがあります。
ナモミは「なずむ」ということで、実が衣服や動物の毛につくことからこの名がつけられたともいわれます。漢名を蒼とか耳璫のというのは、実が婦人の耳飾りに似ているからです。
オナモミの果実は、解熱、発汗、頭痛などの薬用として使われ、生の茎や葉の搗き汁は湿疹や虫さされに塗って効果があるといわれます。
オナモミのほか、オオオナモミ、イガオナモミ、トゲオナモミ等が帰化しています。

崖の灯やなお生き恥のからすうり
落葉した後も
花は八月~九月に、お化けのような白い花が、日が沈み夕闇がせまるとともに咲き始めますが夜の十時頃にはすでに咲きはじめたころの精彩がなくなり、翌日の朝にはほとんどしぼんでしまいます。
茎は稜があって細く、葉の柄の反対側から枝分かれする巻ひげが出て他物にからみながら伸び三米以上にもなり、著しく枝分かれして低木などをおおい、また木によじのぼります。
根は塊状に肥大し、これからデンプンをとりキカラスウリの根の代用品として使います。果実は民間楽としてはだ荒れ、ひび、やけどなどに用い若い果実は漬物にすることがあります。
夏の夕暮れ、家族でこの花を訪ねてみませんか。

「七
ナズナの語源には、愛称としての
ナズナの根生葉はダイコンの葉に似ていて、写真のように車座に地面にへばりつきロゼットを作ります。二~六月に白い十字形の小さい花が花茎の下の方から次々に上に咲いていき、頂の花が咲く頃は下の方にさかさ三角形の平たい果実ができます。この果実の形が三味線の撥に似ているのでペンペングサの名があり、地方によっては、シャミセングサ、チロリンという方言もあります。
ナズナは民間薬として、毒消し、利尿、止血などに効果があるといわれます。身近にあるナズナを採集し、「七種がゆ」を作ってみませんか。

庭木や庭石の上、かやぶき尾根の軒、低山地の岩の上や木の幹などにも着生するウラボシ科の常緑性のシダで、日本全国に分布しています。
耐寒性が強く、短くはう根茎から細長く先端の鋭い単葉を密に生じ、裏面の上部の中央脈をはさんで円形の胞子嚢群が二列に並んでつきます。シダ類は、花の咲かない、果実のできない胞子によって繁殖する植物で、ノキシノブは葉の裏にできる胞子によってふえていきます。
わが屋戸の軒のしだ草生ひたれど恋忘草見れど生ひなく (万葉集)

「つくし誰の子すぎなの子」という童謡がありますが、ツクシは早春の土手、河原、路傍、線路沿いなどに見られます。
ツクシは、スギナの胞子茎で頭の先は筆の穂形で、緑の粉のような胞子が入っています。ノキシノブと同じくシダ類で花の咲かない植物です。
ツクシが枯れはじめると、緑色の節がある細い枝を輪生する栄養茎がすくすくとでてきます。地面を掘ってみると、地下茎でツクシとつながっているのがわかります。
土筆煮て飯くふ夜の台所 (正岡子規)
ツクシは早春若くみずみずしいうちに摘み、袴をとって、土筆和、佃煮、酢のものなどにして食べられます。
私たちは普通、栄養茎のことをスギナと呼んでいますが、スギナは生活力が強く、除草しにくい雑草でもあります。これは地下茎が発達しているからです。似た種類にイヌスギナ、トクサ、イヌドクサがあります。