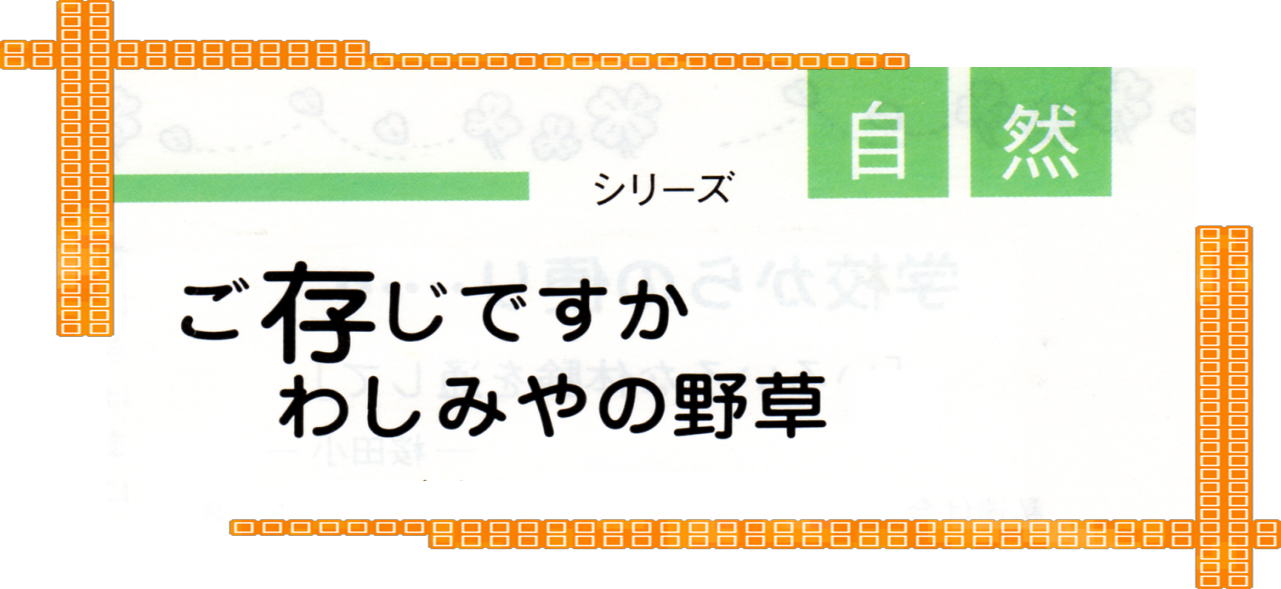
広報わしみや No.273~278
平成5年4月~平成5年9月
 水辺、湿った道ばた、水田のあぜ、水田の中などに普通に見られる植物。秋稲の刈取り後に芽生え、ナズナやタンポポのようにロゼット葉で冬を越し、春になると急激に成長します。冬から春に
水辺、湿った道ばた、水田のあぜ、水田の中などに普通に見られる植物。秋稲の刈取り後に芽生え、ナズナやタンポポのようにロゼット葉で冬を越し、春になると急激に成長します。冬から春にかけて、スズメノテッポウとともに水田に最も多く生える雑草です。
茎は下の方で枝分かれし、上の方は直立し、暗い緑色でしばしば葉柄とともに暗紫色を帯びます。葉は互生し、羽状に深く切れこみ、小葉は3~5対あり、項端のものは大きく、茎とともに細かい毛がまばらに生えます。
花期は3~5月。枝分かれした茎の先に多数の小花が並び穂のようになります。花弁は4枚で白色、長さ3~4ミリでほかのアブラナ科の花と同じようなつくりをしています。このなかまは、がく片4個、花弁4個が十字形に並ぶので十字花科ともいわれ、古い植物図鑑では「じふじばな科」となっています。花は下から順々に咲き、さやは細長く約2センチ、種子が一列に並び熟すとからが二つに裂けて種子をはじきとばします。
稲の種籾(たねもみ)を水に漬(つ)けて、苗代(なわしろ)をつくる準備をする頃に花が咲くので種漬花と名づけられました。若い苗や葉を摘んで、塩もみ、漬物、浸し物などにして食べます。
分布が広いため変化が著しく、いくつかの型が区別されており、乾燥地に生え、毛が多く茎が立ち、葉が細かいものをタチタネツケバナと呼んでいます。
(写真や青毛堀川畔にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎
 畑地や水田のあぜ、道ばた、荒れ地などに普通に見られる植物。種子でふえ、秋に芽生えて冬を越し、春さきの畑地などに多く発生します。
畑地や水田のあぜ、道ばた、荒れ地などに普通に見られる植物。種子でふえ、秋に芽生えて冬を越し、春さきの畑地などに多く発生します。小形の草で茎は柔らかくて無毛。紅紫色を帯び根もとで枝分かれして地面に広がり細い枝を伸ばします。こんもりとした株になることがあります。葉は細い楕円形で先がとがり、柔らかくて無毛、対生して葉柄はありません。
花期は3~6月ですが、日当たりのよいところでは冬でも咲きます。花は枝分かれした茎の先に花柄を伸ばし、その先がまた枝分かれしてそこに白い小さな花をつけます。花弁は5枚ですが二つに大きく切れこんでいるので10枚に見えます。雄しべは5~7本、花柱は3本。花の大きさは約8ミリで目立ちますが、夏の花は花弁が小さく、ときには消失することがあります。
ノミノフスマの名は蚤(のみ)の衾(ふすま)の意味で、この草の葉が小形であることからノミの夜具(やぐ)に見たてたものです。似た種類にノミノツヅリがあります。ノミノツヅリは、茎がややかたく、茎や葉に細い毛があり、全体がまばらな感じで広がります。花弁は5枚ですがノミノフスマのように切れこみはありません。ノミノツヅリ(蚤の綴)の名は小さい葉を蚤の衣に見たてたものです。花は白色、5ミリほどの大きさで4~6月に咲きます。
(写真はノミノフスマ、福祉センター付近にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎
 はじめ白色の花が、のちに淡黄色に変わる香りのよい花が葉のつけ根のところに2個並んで咲く常緑のつる性の低木。白花と黄花が混(ま)じって咲くので金銀花、金銀カズラともいわれます。
はじめ白色の花が、のちに淡黄色に変わる香りのよい花が葉のつけ根のところに2個並んで咲く常緑のつる性の低木。白花と黄花が混(ま)じって咲くので金銀花、金銀カズラともいわれます。林の縁(ふち)や道ばたのやぶ、垣根などに生育し、地下茎でふえます。花期は5月下旬から6月。花の管の細いほうを吸うと甘いのでスイカズラの名がついたともいわれます。また、冬でも葉の一部が残っているため忍冬ともいわれます。秋に、青黒色をした球形の果実(液果)を結びます。
葉は長だ円形または卵状だ円形で、裏側の脈上に毛が多く、若い苗の葉は羽状に裂(さ)けますが普通は切れこみはありません。葉は散らず、外側に巻き上がって冬を越します。茎はつる性で右巻に他の木や針金などに巻きつきます。枝はのびるのが早く、花の頃には60センチ以上にのびています。(花はその年のびた枝の葉のつけ根につく)
スイカズラは漢方薬としても知られ、茎や葉を乾そうしたものを忍冬(にんどう)といい、花のつぼみを乾そうしたものは金銀花といわれます。ともに煎(せん)じて飲めば利尿、健胃、解熱に効果あり、風呂に入れて入浴するとからだが温まって、痔の痛み、腰痛、関節炎などによいといわれます。
(写真は東大輪地内にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎
 冬川の石の間の流れ水流れ清みて芹生ひにけり 若山牧水
冬川の石の間の流れ水流れ清みて芹生ひにけり 若山牧水春の七草の一つとして古くから知られるセリは、たんぼの溝や湿地などに生育します。この牧水の歌は湿地を好んで生えるセリの生態を見事にとらえています。
セリは独得の香りと風味があり、冬から春にかけて生育するので、春先の野菜として栽培もされます。たんぼなどに生えるのを田ゼリといいます。葉は2回羽状の複葉で、小葉は切れこみがあります。茎は細かく枝分かれして立ち、高さ30~50センチ、時には1米にもなり、細長い地下茎をひいてふえます。
七~八月に、枝先に多数の白色の花をかさ状につけます。花径は2~3ミリ、5枚の花弁と
5本の雄しべがあり、果実は長さ2~3ミリのだ円球で秋に熟します。
料理では、セリはゆでてひたし物やあえもの、汁の実、なべ物などに用いられます。鴨芹なべ焼が有名で、「なべ焼の鴨と芹とは二世の縁(えん)」という江戸川柳もあります。薬用としては、神経痛、リューマチや小児の解熱によいとされています。
似た種類のドクゼリは猛毒植物ですから注意が必要です。ドクゼリの地下茎は、セリにくらべて太く、節(ふし)がたくさんあるのでわかります。
(写真は、給食センター付近にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎
 空き地、やぶ地、家の周囲などいたるところに生えるつる性の多年生植物。長い地下茎を横にのばし、ところどころから芽をだします。地上に出た茎は枝分かれしてよく伸び、他の草や木におおいかぶさります。生長が早く、藪を枯らすほどよく繁殖するのでヤブガラシといいます。家の周囲に生えると植え込みや屋敷がとり囲まれいかにもみすぼらしく見えるようになるのでビンボウカズラという別名もあります。
空き地、やぶ地、家の周囲などいたるところに生えるつる性の多年生植物。長い地下茎を横にのばし、ところどころから芽をだします。地上に出た茎は枝分かれしてよく伸び、他の草や木におおいかぶさります。生長が早く、藪を枯らすほどよく繁殖するのでヤブガラシといいます。家の周囲に生えると植え込みや屋敷がとり囲まれいかにもみすぼらしく見えるようになるのでビンボウカズラという別名もあります。新芽は濃い赤褐色で軟毛があり、のびた茎(つる)にはりょう(稜)があります。葉は互生で長い柄があり鳥足状の五枚の小葉に分かれ、葉の反対側に巻きひげ(茎の変形)がでます。ひげは先が二つに分かれ、このひげで他物にからみつきながら茎は五~六メートルにものびます。
花期は七~八月、花をつける枝は葉と向かいあってふさ状に集まった小花をつけます。花弁は四枚で緑色そのもとの方は花盤という橙色の盤上の部分で花弁が落ちると目立ちます。花にはアオスジアゲハがよく集まります。花後、紫黒色のブドウのような小さい果実をつけます。
新芽やつる先は食用になります。普通は塩を加えてゆで、水にさらしてから調理します。薬用には、根を煎じて消炎、解毒、鎮痛、利尿薬などに利用されるほか、はれものや毒虫に刺されたときに茎葉の生汁をつけるとよいといわれます。
(写真は東大輪地内にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎
 ひるがへる葛の大葉や山雨急 染谷多賀子
ひるがへる葛の大葉や山雨急 染谷多賀子秋の七草の一つとして万葉の昔から親しまれてきた植物。茎はつる状になって一〇メートル以上にもなり、枝分かれしながら左巻きで他物にからみつきます。茎のもとの方は木質化します。
葉は長い柄があって互生し、三枚の小葉に分かれ、裏面に白い毛が密生し白色をおびます。風を受けてヒラヒラと裏をみせる風情が美しく、裏見草の名があります。また、葉は睡眠運動が盛んで、夜は垂(た)れて裏面を合わせて眠り、晴天の日中は表面を合わせ (クズの昼寝)ます。
花期は七~九月、写真のような紅紫色の花を密集してつけ、下から順に上の方へ咲いていきます。花後、かっ色のあらい毛が密生する七~八センチのさやができます。昔はクズのつるを材料にして葛布(くずふ)を織って着物にしたり、葉を家畜の飼料にしていました。
根は長さ一メートル以上、直径二〇センチにもなり、デンプンを多量に含んでおり、そのデンプンが葛粉(くずこ)です。奈良県吉野地方は、昔から葛粉の名産地で、吉野国栖(くず)の人々が葛粉をつくり、京の都へ売りに釆たことからこの名が生まれたといいます。根は漢方薬の葛根湯(かっこんとう)の原料として有名。葛粉を熱湯にとかしたものを葛湯といい、昔から感冒などで悪寒を伴う時に用います。また、二日酔いには乾そうしたクズの花を煎じて飲むとよく効きます。
(写真は東大輪にて撮影) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎