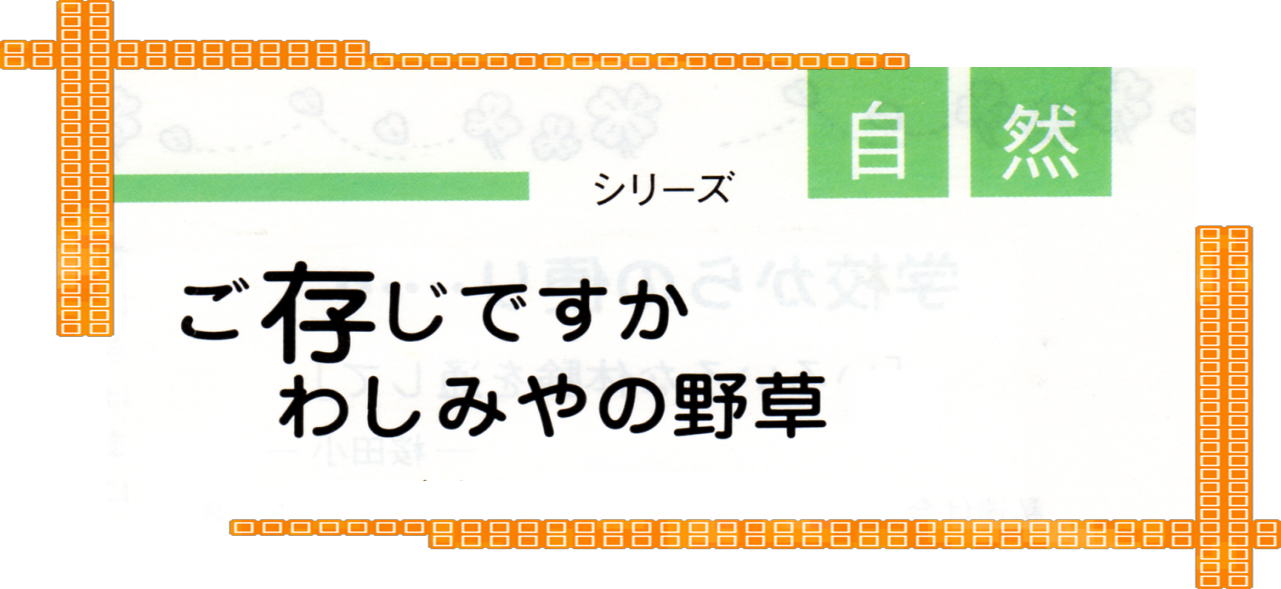
広報わしみや No.387~392
平成14年10月~平成15年3月
 南アメリカ原産で、世界の熱帯から温帯にかけて広く帰化している多年草です。日本では大正年代に帰化しました(一九一五年に小笠原で初めて採集)。戦後急に多くなり、現在では北陸、関東以南で雑草化しています。現在、町内の草地や空地、道ばたなどいたるところでみられ、在来種のスズメノヒエ(雀の稗)よりはるかに多く分布しています。
南アメリカ原産で、世界の熱帯から温帯にかけて広く帰化している多年草です。日本では大正年代に帰化しました(一九一五年に小笠原で初めて採集)。戦後急に多くなり、現在では北陸、関東以南で雑草化しています。現在、町内の草地や空地、道ばたなどいたるところでみられ、在来種のスズメノヒエ(雀の稗)よりはるかに多く分布しています。茎は根元から何本も分かれ出て、高さ一メートルに達します。葉は、長さ十~二十五センチ、幅五~十二ミリ、葉鞘(ようしょう)の口部以外は無毛です。茎の先に長さ七~十センチの穂の枝を四~八本出し、下面に三~四列に小穂をつけます。小穂のへりには綿糸のような長毛があります。葯(やく)も柱頭も黒紫色です(写真右下参照)。花の咲く時期は七~十月です。
グリスグラスと呼ばれ、暖地型牧草として栽培されます。

在来種のスズメノヒエは、全体がやや小さく、葉身・葉鞘ともに長い毛があり、小穂のへりは、無毛、葯は黄色なので見分けられます。
似た種類には、スズメノヒエのはか、キシュウスズメノヒエ、ナルコビエがあります。
【写真左上、右下ともに上内地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 本州の福島県以南に分布し、沼地の比較的澄んだ水を好んではえます。水田、特に休耕田にはコナギ(わしみやの野草55参照)などとともに群生します。
本州の福島県以南に分布し、沼地の比較的澄んだ水を好んではえます。水田、特に休耕田にはコナギ(わしみやの野草55参照)などとともに群生します。茎はたばになってはえ、高さ四〇~九〇センチになり、丸くてたくさんの横の隔膜(かくまく)で仕切られ、指で押すとパチパチと音を立ててつぶれます。
葉はすべて退化してさやとなり、茎の基部をつつみます。八月から十月のあいだに、茎の先に黄褐色の子穂を一個つけ、その太さは茎とほぼ同じです。(写真右下参照)
夏から秋にかけて地下径の先のたくさんの※塊茎(かいけい)(直径一センチ以下のクワイのような塊茎)を作って冬
 を越します。塊茎は耕土の一〇~二〇センチの深さにできます。翌年この塊茎から新芽を出し新しい株になります。水田の雑草として最近発生量が多くなっているのは、こうした冬の越し方が一因になっているようにも考えられます。この塊茎はエグ味が強くて食べられませんが、塊茎がクワイに似ているのでクログワイの名前が生まれました。中華料理によく出てる黒慈姑は中国産のオオクログワイの塊茎です。
を越します。塊茎は耕土の一〇~二〇センチの深さにできます。翌年この塊茎から新芽を出し新しい株になります。水田の雑草として最近発生量が多くなっているのは、こうした冬の越し方が一因になっているようにも考えられます。この塊茎はエグ味が強くて食べられませんが、塊茎がクワイに似ているのでクログワイの名前が生まれました。中華料理によく出てる黒慈姑は中国産のオオクログワイの塊茎です。※塊茎…地下茎の先端に養分を蓄え、大きくなったもの
【写真左上、右下とも上内地内休耕田にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 大利根の流れたゆたふ萩の花 長須蛸玲子
大利根の流れたゆたふ萩の花 長須蛸玲子一般にはススキと思って眺めている人も多いかもしれませんが、ふさふさした銀白色の穂先を輝かしたオギの群落が町内各地で見られます。
ススキ(わしみやの野草30を参照)は山野の日当たりのよい、やや乾いたところに群生する多年草ですが、オギは水辺や湿地に生(は)える多年草です。地下茎(ちかけい)は長く横にのび、茎は一本ずつ立って、ススキのようにたばになることはありません。直立した茎は一~二・五メートルになります。利根川などの河原にはしばしばオギの大群落が見られます。
ススキとオギはとてもよく似ていますが、オギの小穂(しょうすい)には芒(のぎ)がなく、基部(きぶ)には小穂の三~四倍長い絹糸のような銀白色をした毛があるのでススキと見分けられます。(写真右下参照)
実際には、湿地に生(は)えていて、ススキよりふさふさした花穂
 のようすで、なれてくると遠くの方から見ただけで分かるようになります。
のようすで、なれてくると遠くの方から見ただけで分かるようになります。花の時期は九~十一月で、日本全土に分布しています。昔はオギを荻と書き、薄(ススキ)別名尾花とは、はっきり区別していました。
※ススキは薄または芒で表記されることがあります。芒は漢名、薄は俗字。
【写真左上は桜田三丁目地内、右下は上内地内にて撮影】
写真と文 長須 房次郎
 昔から、葉の形が家紋や鎧(よろい)の縅(おどし)に用いられて有名なオモダカは、全国の湖沼の水辺や用水路などにはえます。が、最も普通に見られるのは水田です。除草剤のため最近少なくなっていますが、今でも休耕田や水田に生育しています。
昔から、葉の形が家紋や鎧(よろい)の縅(おどし)に用いられて有名なオモダカは、全国の湖沼の水辺や用水路などにはえます。が、最も普通に見られるのは水田です。除草剤のため最近少なくなっていますが、今でも休耕田や水田に生育しています。葉はすべて根元から出て柄が長く、葉身は、矢じり形で下側が左右に広く裂(さ)けます。オモダカの和名はその葉の様子が面高(おもだか)な顔に似ているところからきているといわれます。
花は花茎の上方に雄花が、下方に雌花が三個づつつきます。(写真右下参照)花期は、七~十月です。
秋になると株元からストロン(走出枝)が伸び先端に塊茎(かいけい)ができます。この塊茎から翌年春から芽を出します。だらだら芽吹
 くので採っても採っても出てきます。これはオモダカのしたたかに生きるための戦略といえます。この塊茎が大きくなるように改良されたのが、慈姑(くわい)です。慈姑は塊茎から勢いよく伸びる大きな頂芽(ちょうが)にあやかり、立派な芽が出るようにと正月や祝い事の料理に使われます。ちなみに主産地は越谷・草加・さいたま市の水田地帯で全国の八〇%を生産しています。
くので採っても採っても出てきます。これはオモダカのしたたかに生きるための戦略といえます。この塊茎が大きくなるように改良されたのが、慈姑(くわい)です。慈姑は塊茎から勢いよく伸びる大きな頂芽(ちょうが)にあやかり、立派な芽が出るようにと正月や祝い事の料理に使われます。ちなみに主産地は越谷・草加・さいたま市の水田地帯で全国の八〇%を生産しています。【写真左上、右下とも宝泉寺池近くにて撮影】 写真と文 長須 房次郎
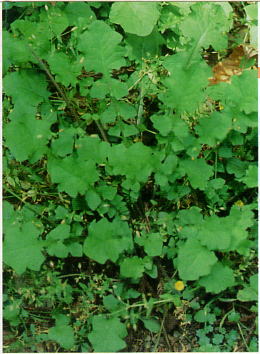 春の七草のひとつの「仏の座」はタビラコ別名コオ二タビラコ(わしみやの野草59参照)ですが、今回登場するのはヤブタビラコです。タビラコに非常によく似ているので、七草粥を作る時、ヤブタビラコを摘んでしまったという話をよく聞きます。
春の七草のひとつの「仏の座」はタビラコ別名コオ二タビラコ(わしみやの野草59参照)ですが、今回登場するのはヤブタビラコです。タビラコに非常によく似ているので、七草粥を作る時、ヤブタビラコを摘んでしまったという話をよく聞きます。ヤブタビラコの名前は藪(やぶ)や木陰にはえるタビラコという意味でつけられました。
ヤブタビラコは、林の中やまわり、土手など湿り気の少ないところにはえる二年草ですが、タビラコは水田などの湿地にはえる二年草です。
ヤブタビラコは、大部分の葉は根元にあって、長さ五~十五センチで羽状に深く裂けています。立ち上がった茎には小さな葉が一~三個つきます。茎や葉にはまばらな毛がありますが、タビラコの葉に毛はありません。
花期は四~六月、頭花は黄色で直径は約八ミリで
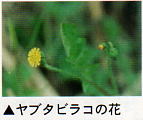 す。総包(そうほう)ははじめ楕(だ)円形ですが、花がすむと閉じてほとんど球形になります。その後、開いて赤褐色の果実を外に出します。果実には冠毛はありません。タビラコの総包は花がすんでも円筒形ですから、見分けるときの決め手になります。(右下の写真参照)
す。総包(そうほう)ははじめ楕(だ)円形ですが、花がすむと閉じてほとんど球形になります。その後、開いて赤褐色の果実を外に出します。果実には冠毛はありません。タビラコの総包は花がすんでも円筒形ですから、見分けるときの決め手になります。(右下の写真参照)オ二タビラコ (わしみやの野草62参照)は荒れ地、畑、庭などにはえる二年草です。
【写真左上は鷲宮神社付近、右下は八甫地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 畑のなかや乾いた道などに生える二年草で、白色の直径五ミリほどの小さな花を咲かせる世界中の耕地雑草で、日本全域にみられます。
畑のなかや乾いた道などに生える二年草で、白色の直径五ミリほどの小さな花を咲かせる世界中の耕地雑草で、日本全域にみられます。茎は細く、根もとからいちじるしく枝分かれして短い毛を密生します。(下向きの毛が多い)葉は柄がなく対生し両面とも毛があります。花期は三~六月で、花弁は楕円形で先がまるく、がく片より短く先がまるく、長さ約二ミリです。がく片は先がとがり長さ約三ミリでヘりが膜質で背面には※腺毛(せんもう)があります。果実は熱すると先が六裂し、多くのこまかい種子をはきだします。
似た種類のノミノフスマは、①茎や葉には毛がなく柔らかい感じ②こんもりとした株になる③花弁は五枚で深く二裂し、がく片より長い④がく片は無毛⑤葉はやや細い楕円形で大きい。という点でノミノツヅリと見
 分けられます。(わしみやの野草38参照)
分けられます。(わしみやの野草38参照)ノミノツヅリの名について、牧野日本植物図鑑(昭和二十九年版)には「和名ハ蚤の綴り二シテのみノ短衣(たんい)即チ※※つづりノ意ナリ、蓋(けだ)し本種ノ小形葉ヲ蚤ノ衣二擬セシモノナラン」 と記されています。
※腺毛…毛の一種で粘液などを分泌するもの。
※※つづり (綴り)…つぎあわせた着物。粗衣。
【写真左上、右下とも県道栗橋川越線(砂原小付近)にて撮影】 写真と文 長須 房次郎