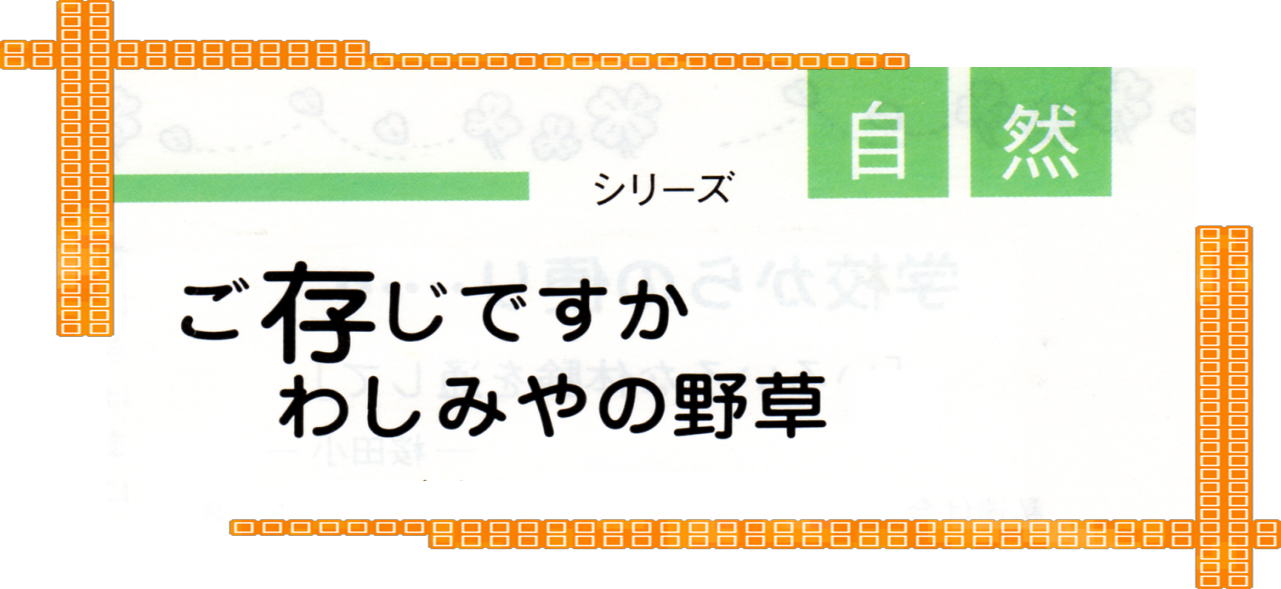 広報わしみや No.249~254
広報わしみや No.249~254平成3年4月~9月

タンポポは最も代表的な春の野草で、土手、道ばた、野原など町内各地に見られます。
写真は、カントウタンポポで、昨年四月十日、青毛堀川の土手(粟原)で撮影したものです。
タンポポ属の学名タラクサカムは、ギリンヤ語の「苦痛」と「いやす」との複合語で、このことからわかるように古代から健胃、催乳の薬に用いられています。
頭花は、舌状花が何列も重なっていて、筒状花はなく、日が照ると開き、かげると閉じるので、西洋では 「牧童の時計」とも呼ばれます。
シロバナタンポポは、関東地方以西、四国、九州に分布している種ですが、町内にも数ヶ所見られます。タンポポは一般に虫媒花で、昆虫によって運ばれた花粉が雌しべについて受精する両性生殖をしますが、受精をしないでふえる(単為生殖)種もあります。
セイヨウタンポポは、明治初年、札幌農学校の教師ブルックスが野菜用に北米から種子を入れて栽培したものが野性化したといわれますが、現在では在来の日本種をすっかり圧倒してしまいました。単為生殖をし、かつ年中花が咲くので春しか咲かないカントウタンポポより種子がたくさんでき、病虫害にも強いためであると考えられます。総苞片が開花時にもそり返っているのが特徴です。
タンポポの花や葉は、てんぷらにしておいしく食べられます。
鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

四つ葉のクローバーは幸福のシンボルとして珍重されますが、クローバーの代表的な種類がシロツメクサです。シロクローバー、オランダゲンゲとも呼ばれます。徳川時代にオランダから輸入したガラス器具のつめ物として、シロツメクサの乾草が使われており、そのなかの種子から発芽したので
白又は淡紅色の蝶形の花が、葉えきから出た花の柄の項に、傘形に平均70の花がほぼ球形に集まって咲きます。花弁は散らずにかっ色をおび、ながくついています。
葉は互生する三枚の複葉で、表面に斑紋をもつものが多く、茎は地面を長くはって、節から根を出してよくのびます。通常、ミツバチにより他花受粉をします。
似た種類に、ムラサキツメクサがありますが、やはりヨーロッパ原産の帰化植物で、アカツメクサともいわれ、日本へは江戸時代に伝わったといわれますが、牧草として北海道へ輸入されたのは明治初年のことです。
休日に四つ葉のクローバーをさがしてみませんか。
写真はシロッメクサの群落(中川堤防) 鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

やや湿り気のある道端や日陰にふつうに見られ、群生し、全体に臭気がある植物で地中を長くはう白い地下茎から軟らかい地上茎を直立して、盛んに繁殖します。
茎も葉も赤紫色をおび、五~七月に穂状花序をつけますが、白い四枚の花弁のように見えるのは、植物学的にいうと総苞で、この中心にある太く短い黄色の穂が、花弁もがくもない小さな花の集まりです。
ドクダミは、二〇〇〇年も前から薬草として使われてきました。ドクダミという和名は、昔の江戸の方言であり、毒痛みの意味だといわれます。十薬は漢方に由来する名前です。十薬といわれるように、さまざまな薬効があるといわれます。
最近、どくだみ茶を愛用されている方が多いようですが、私たちの健康とのかかわりの深い植物の一つとして注目されています。ドクダミの薬効成分は、梅雨の頃の開花時に最も高いといわれます。
ドクダミは日陰の雑草ですが、小鉢に植えて眺めると楽しめます。短歌にも詠まれています。
色硝子暮れてなまめく町の湯の窓の下なるどくだみの花(北原白秋)
鷲宮町立図書館長 長須房次郎

野原や道端など町内いたるところに見られる踏みつけられても平気な強い草―どんな高い山に登っても、人の歩く道があるかぎり、オオバコの生えていないところはないといわれるほど、雑草として名を売っているのがオオバコです。
葉が広くて大きいので大葉子の和名がつけられ、葉を火であぶって指先で軽くもむと、その部分の表皮がまるくふくれあがるのでカエルッパ又はゲエロッパともいわれます。中国では、牛馬車の通る道端に多いというので車前草といいます。
種子を漢方では車前子といい、煎じて飲めばぜんそく、胃腸病、利尿、止血などに効くといわれます。若い葉は食用にもなり乾そうしてお茶として飲むこともあります。採取時期は夏。
白い小さな花が五~九月の間花茎上に細長いひも状に咲き、種子は水気をおびるとねばり気が出て、靴の裏などについて牛馬や人とともに広がりますので、オオバコは人間くさい植物です。
似た種類にヘラオオバコ (ヨーロッパ原産の帰化植物)があり、荒れ地、砂地などに見られます。
― ふまれつつ車前草のたくましき ―
鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

日当たりのよい畑、道端、あき地、公園、庭さきなどに普通に見られる一年草。全草多肉質で無毛、葉は互生又は対生し、又枝先に集まる。
七月から九月にかけて、黄色い小さい花を枝の先に三~五個つける。花には柄がなく、花弁は五枚、さかさ卵形で先がくぼんでおり長さが約四ミリ、おしべは七~十二本で黄色、
スベリヒユの若い茎や葉は茹でて、ゴマあえ、三杯酢などにして食べる。たくさん食べると下痢をするが、民間薬として煎じて利尿、解毒などに用い、また毒虫に刺されたとき茎葉をもんで塗るなど用途が広い。採取時期は七-八月、開花前が最適。昔は乾燥して貯蔵し非常食としました。
スベリヒユの名は、茹でるとぬめりがでることに由来し、イワイヅル、ヒデリグサ、スベリビ、ツルツル、ヨゴシグサ、トンボグサ等の別名もみなこの草の特徴をあらわしています。
似た種類に栽培品のタチスベリヒユがあります。夏の花壇を彩るマツバボタン(松葉牡丹)はスベリヒユと同じ仲間で、原産地は南アメリカ、日本へは江戸時代の末ごろ(弘化年間)渡来しました。
滑莧これしきの身のおきどころ(清水径子)
鷲宮町立図書館長 長須 房次郎

茎は太くて直立し、先の方が弓なりに曲がり中空。若い茎は軟らかく、たけのこ状で、太いものは直径四センチにもなり地下茎から出て群生します。正岡子規の「山陰に虎杖森の如くなり」はイタドリが生い茂っているようすをよく表わしています。
若い茎は、シュウ酸を含むため酸味があり、生食したり、皮をむき水にさらして煮たり、塩漬にして保存山菜とし、乾燥した若葉はタバコに混ぜたり、または代用として使いました。中国では、若い茎の紅紫斑を虎の皮の模様にたとえて「虎杖」といいます。根は地下茎とともに薬効があり、通経、利尿、緩下剤などに用いられます。痛み取りの薬効があるのでイタドリと名づけられたといわれます。
イタドリは分布が広いため変異が著しく、葉に毛の多いものをケイタドリ、葉が厚く光沢のあるハチジョウイタドリ、花、果実が赤く染まるメイゲツソウ、高山の日当たりのよい草原に生えるオノエイタドリなどに区別されます。
似た種類のオオイタドリは、富山以北の裏日本、北海道に分布しています。
鷲宮町立図書館長 長須 房次郎