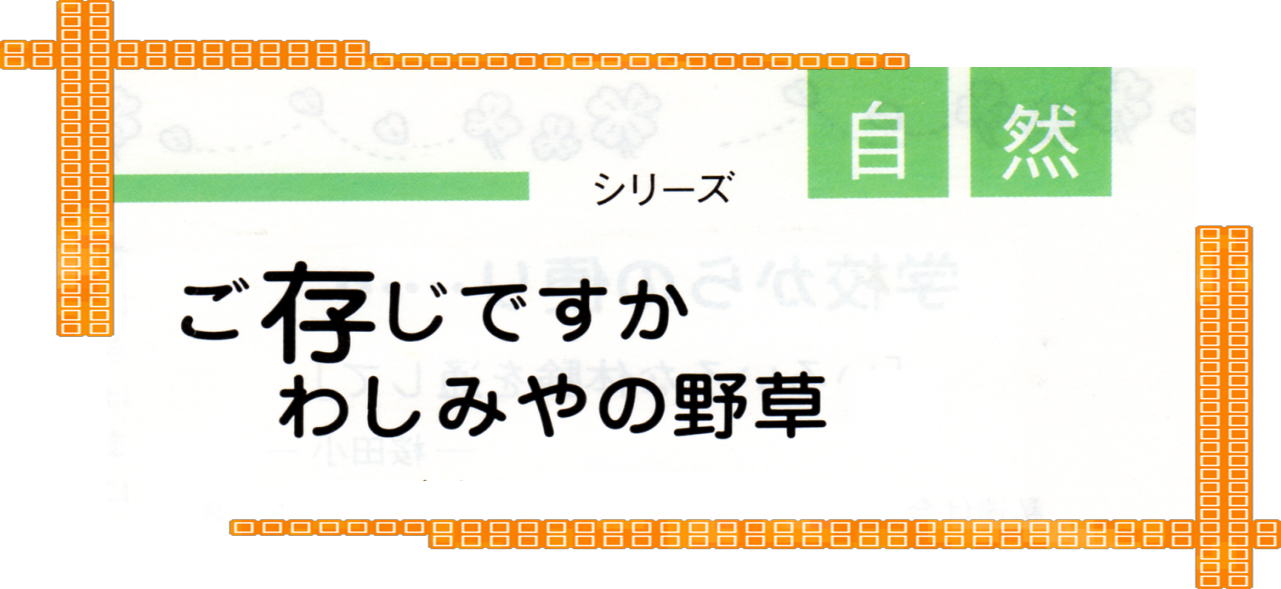
広報わしみや No.363~368
平成12年10月~平成13年3月
 草原やあぜ道などの日当たりのよい湿地に生える多年草で、町内ではあぜ道で見られます。
草原やあぜ道などの日当たりのよい湿地に生える多年草で、町内ではあぜ道で見られます。茎は高さ二十~六十センチになり、伏せた軟毛があって、地下茎をひいて繁殖します。
葉は長さ五~十センチ、幅は二センチ内外で、両面に伏し毛があり基部はやや茎を抱きます。花の頃には下部の葉は枯れてなくなってしまいます。
花は茎の上部の枝先に咲き、直径三~四センチあり、舌状花(*ぜつじょうか)は数が多く、舌(ぜっ)片の先にははっきりした三個の歯があります。
花の咲く時期は七月から十月で、稲が刈られた後でも水田の縁などに咲いているのが見られます。

オグルマの和名は、規則正しく、放射状に舌状花を開く頭花(*とうか)を小さな車に見立てて 「小車」 と名付けられました。右下の写真をみるとその様子がよく分かります。
※舌状花…タンポポやヒマワリのまわりの花のように下部は筒形で花びらの上部が舌のように伸び広がっているもの
※頭 花…花軸の先が円盤状にひろがり、キク科植物の花のように多くの花が集まって一つの花のように見えるもの
【写真左上、右下とも八甫のあぜにて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 大きな一年草で、茎は直立し、高さは三メートル、太さは直径二~四センチにもなり、あらい毛が生え、枝を分けて大きな株になります。葉は大きく、長さ幅ともに二十~三十センチになり、両面ともざらつきます。葉が桑に似ているのでクワモドキの別名があります。
大きな一年草で、茎は直立し、高さは三メートル、太さは直径二~四センチにもなり、あらい毛が生え、枝を分けて大きな株になります。葉は大きく、長さ幅ともに二十~三十センチになり、両面ともざらつきます。葉が桑に似ているのでクワモドキの別名があります。北アメリカ原産で、日本には戦後(一九五二年)入ってきました。十年前には町内ではほとんど見られませんでしたが、現在では中川の河川敷や堤防、道ばた、荒れ地などのやや湿ったところで見られるようになりました。(一年草ですが河川敷などに大群落をつくることがあります)
花の咲くのは八~十月ですが、十一月上旬でも見られます。花のつくりはブタクサ(わしみやの野草21参照)によく似ており、雄(おす
 )の頭花が長い穂となり、その下に雌(めす)の頭花がつきます。
)の頭花が長い穂となり、その下に雌(めす)の頭花がつきます。アメリカでは六メートルになるものもありバッファロー・ウィード(野牛草の意味)と呼ばれています。風媒花(ふうばいか)で大量の花粉を吐き出し、ブタクサとともに花粉症の原因になります。
※風媒花は風によって受粉する花。マツ、スギ、クワ、イネなどの花の類。
【写真左上、右下とも中川堤防にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 道ばたや畑地、河原にはえるありふれた一年草または二年草です。
道ばたや畑地、河原にはえるありふれた一年草または二年草です。キュウリグサ(わしみやの野草84参照)と同じようなところにはえ、植物全体がキュウリグサに似ています。
茎や葉が大形で、まわりに細かい毛が密生し、花のつけ根には小葉(包葉)があるので区別がつきます。また、キュウリグサはもんで臭いをかぐとキュウリのような香りがしますが、ハナイバ
 ナはしないので区別がつきます。
ナはしないので区別がつきます。茎は下部で何回も枝分かれして、地面近くに半ばはうようにしてのび、上部は斜めにたちます。
花期は三月から十二月上旬まで、花は直径約三ミリ、淡いあい色をしています。花後、だ円形で表面に突起のある果実 (分果(ぶんか))を四個つけます。キュウリグサの分果はなめらかです。
葉と葉の間に花がつくので「葉内花(はないばな)」の名前がつきました。
【写真左上、右下とも西大輪地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 常緑性のシダで、東北地方から九州まで広く分布しています。山地の林下や崖(がけ)、人里付近に普通で、市街地でも見られます。
常緑性のシダで、東北地方から九州まで広く分布しています。山地の林下や崖(がけ)、人里付近に普通で、市街地でも見られます。ヤブソテツの名の由来は、明らかではありませんが、茂みの中にソテツのように葉を広げていると見たててつけられたようです。
根茎(こんけい)(根のように見える地下茎)が太く短く葉を叢生(*そうせい)します。
葉柄はわら色で長さ一〇~三〇センチ、葉身は長さ八〇センチ、幅二〇センチにもなります。
葉は羽状に分かれ、羽片は一〇対以上あります。羽片は鎌状で、羽片の基部前側がやや耳状に突き出て
います。葉質は厚い紙質、緑色で光沢はありません。
胞子嚢群(*ほうしのうぐん)は右下の写真のように、円形で、羽片の裏面に多数散在します。胞子は初夏に熟します。

ヤブソテツの変種にヤマヤブソテツ、ミヤコヤブソテツがあります。ヤブソテツの仲間は、観葉植物として 庭に植えたり、鉢植えにして室内インテリアに利用されます。
※叢 生…一つの節から多数の葉や茎がでること。
※胞子嚢群(ほうしのうぐん)…内部に胞子を生じる細胞または組織を胞子嚢
(ほうしのう)といい、胞子嚢が数個ないし多数集まったものを胞子嚢群という。
【写真左上、右下とも西大輪地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 ぎしぎしや川とも言へぬ小流れに 田中苳代(とよ)
ぎしぎしや川とも言へぬ小流れに 田中苳代(とよ)春になると右下の写真のように、日当たりのよい道ばたで、ホウレンソウに似た葉を放射状に出して生えているのがギシギシです。
野原、田畑や溝、用水の縁(ふち)などの湿り気のあるところに生える大型の多年草です。
茎は高さ一メートルにもなり、下部の葉は長柄があり長さ一〇~二五センチ、幅四~一〇センチと大きいですが、上方の葉は幅がせまく無柄になります。
花期は五~八月で、茎の先に淡緑色の小さな花の穂をつけます。枝のまわりに何段も輪をかさねたようにつき、一段ごとに葉の形の包(ほう)がつきます。これがギシギシの特徴です。
茎や葉をかむとすっぱいのはシュウサンを多く含んでいるからです。春先に出る葉は食べられますが、食べ過ぎると下痢します。

茎をすりあわせてギシギシと音を出すことからこの名がついたのではないかといわれています。
干した根は漢名で羊蹄根(ようていこん)といわれ、大黄(だいおう)の代用として便秘に煎じて飲むところもあります。
蕎麦殻(そばがら)に似た暗褐色(あんかっしょく)の種子をよく干して、ソバガラの代用に枕に入れると、頭を冷やして気持ちよく眠れます。
【写真左上は青毛掘畔、右下は東大輪にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 北アメリカ原産の帰化植物で、畑、道ばた、空き地に普通に生えます。日本には大正末から昭和の初めに日本に入っていることが気づかれ、現在は日本各地で広く見られるようになりました。
北アメリカ原産の帰化植物で、畑、道ばた、空き地に普通に生えます。日本には大正末から昭和の初めに日本に入っていることが気づかれ、現在は日本各地で広く見られるようになりました。茎は高さ一〇~三〇センチで、全株白い綿毛におおわれています。葉はハハコグサに似て、へら形で幅広く、両面とも綿毛が生えています。
花は春から秋に咲きます。茎の上部の葉のわきに頭状花が集まってつき細長い穂のようになります。これがハハコグサ(ホウコグサ)やチチコグサと違う点です。
「もどき」は他の語に付いてその風采・風情に似たように作り立てられている意を表す言葉ですから、チチコグサモドキはチチコグサまがいの植物ということになるわけです。

ハハコグサは春の七草の一種で昔から親しまれている野草です。(わしみやの野草①参照)
チチコグサモドキに似た種類にウスベニチチコグサ、タチチチコグサ、ウラジロチチコグサ (いずれも帰化
植物)があります。そのうちウラジロチチコグサは一九七〇年代に日本へ入り、関東地方ではすさまじい勢いでふえています。
【写真左上、右下とも八甫集会所周辺にて撮影】 写真と文 長須 房次郎