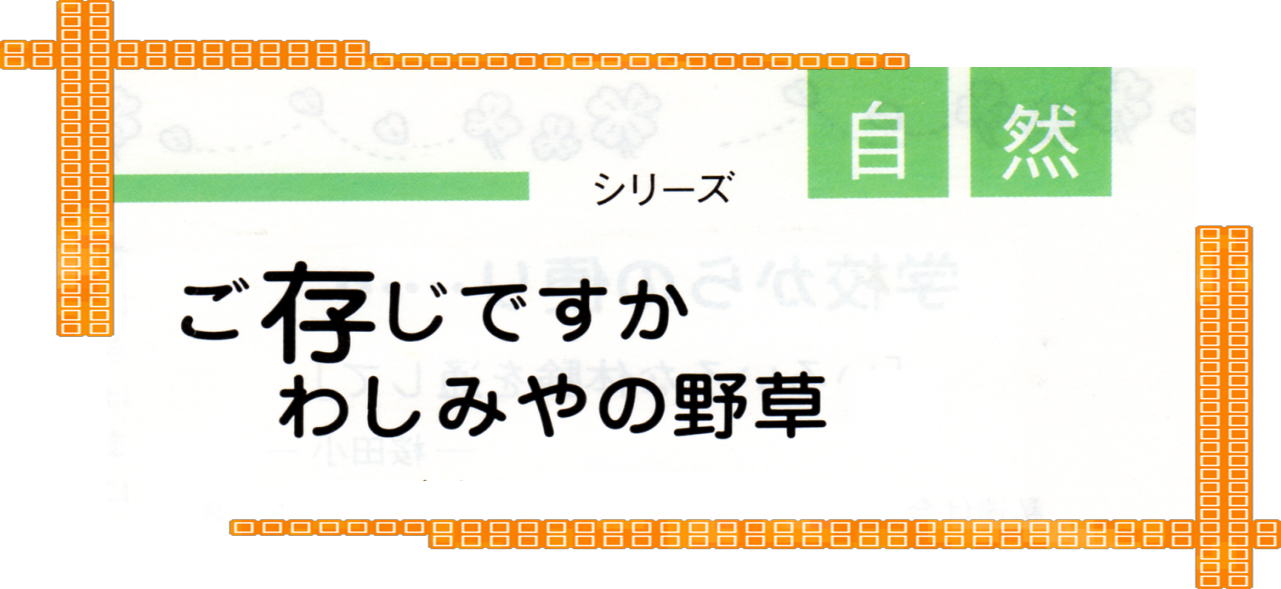
広報わしみや No.357~362
平成12年4月~平成12年9月
 関東地方以西の川岸や水田などの湿った場所に生育する一~二年生草本で、町内各所で見られます。
関東地方以西の川岸や水田などの湿った場所に生育する一~二年生草本で、町内各所で見られます。コイヌガラシの名は、イヌガラシに似ていてそれより小さいから、小形のイヌガラシという意味で子犬のカラシではありません。
江戸末期の本草学者(ほんぞうがくしゃ)飯沼慾斎(いいぬまよくさい)(一七八二~一八六五)の著書『草木図説(そうもくずせつ)』 にコイヌガラシがスカシタゴボウの名で登場しています。
スカシタゴボウは、イヌガラシ (わしみやの野草71参
 照)に似ていますが、果実が小さく、形もちがい、葉の切れ込みが深いので区別できます。
照)に似ていますが、果実が小さく、形もちがい、葉の切れ込みが深いので区別できます。コイヌガラシは、スカシタゴボウに似ていますが葉は下方のものまで小さく、みな羽状に裂けます。
花期は四~六月で、花は黄色で短い柄があり、葉液(ようえき)(葉のつけね)に一個ずつつきます。右下の写真のように、果実は長さ六~十ミリ、幅二~三ミリで上方の葉のわきに一個ずつつき、ほとんど柄がないので他の種類と見分けられます。
【写真左上、右下とも町民温水プール付近にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 乳牛が啼いておどして蛇苺 中村汀女
乳牛が啼いておどして蛇苺 中村汀女ヘビイチゴは、水田の畦(あぜ)や野原、畑の周辺などで普通に見られます。
茎は細く一株から数本出て、地面をはって長く伸びます。節々から根を、出し、そこから分かれて新しい株になります。
葉には長い柄があって三枚の小葉に分かれていますが、ときに下の二小葉が深く裂(さ)け、五小葉にちかいものがまざっています。
花期は四~五月で、黄色い五弁花が長い柄の先に一個ずつつきます。花が終わると花の基部(花床)が肥大して淡紅色になり、そのまわりに淡紅色の小さい粒状の果実がつきます。普通はこれら全体を一つの果実と見なしています。果実(*)は海綿質(かいめんしつ)で汁液がなく、甘味はないが有毒ではありません。でも、食
 べ過ぎないように・・・。
べ過ぎないように・・・。似た種類のヤブヘビイチゴは、半日かげの林内や林のふちにはえ、全形がやや大きく、葉は濃緑色で果実も大きく、色が濃いので区別できます。
※この果実は花床がふくらんだもので偽果(ぎか)(または仮果(かか)) といい、表面の粒が種子です。
【写真左上温水プール付近、右下上内地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 イヌムギは五月のはじめから道ばたや空き地にごく普通にみられるイネ科の植物で、小穂がやや傾いて円すいにまばらについているのでよく目につきます。
イヌムギは五月のはじめから道ばたや空き地にごく普通にみられるイネ科の植物で、小穂がやや傾いて円すいにまばらについているのでよく目につきます。南アメリカ原産の帰化植物で、日本には明治初年に渡来し、北海道から九州まで分布しており県内では丘陵から低地にかけてみられます。
日本名は犬麦、つまり麦に似て有用でないという意味です。茎は根ぎわから束のように数本枝をだし直立し、濃い緑色をしていて平滑(へいかつ)です。葉は平たく、幅五~十ミリで、さやは筒になって茎を包み、白色の柔らかな開出(かいしゅつ)する毛が密生しています。
花期は五月~七月で、小穂は著しく平たく、五~六個の小花がついています。葯(やく)は長さ〇・五ミリほどで花期になっても小花は開かず、自花受粉で実を結びます。

似た植物のヤクナガイヌムギは、前の長さが四~五ミリあり、開花時には黄色い荷をつけた三本のおしべが垂れさがること、護穎(ごえい)の先の芒(のぎ)が十ミリほどあるので区別できます。町内には二種類どちらもみられます。
◆葯(やく)はおしべの先にあって、中に花粉がはいっている袋のような部分
◆護穎(ごえい)はイネ科の花でおしべ・雌しべを包む外側の葉の小片
【写真左上、右下ともわしみや団地周辺にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 烏柄杓千本束にして老いむ 飯島晴子
烏柄杓千本束にして老いむ 飯島晴子畑地に多い多年草で、球形の地下茎(塊茎(かいけい))から長い葉柄のある一~二枚の葉と花茎(かけい)をだします。
葉は三小葉からなり、葉柄の途中(地下)と三小葉のつけね(地上)にそれぞれ一個の球芽(きゅうが)(むかご)ができ、それでふえます。
花茎は長さ二十~四十センチあり、花は葉より高い所につきます。筒形の花(仏炎包(ぶつえんほう))は緑色ときには紫色をおび、筒の部分は長いだ円形でボート形にまがっています。仏炎包の中には一本の花軸があり、筒の部分にかくれて、上の方に雄花、下の方に包とくっ
 つきあった雌花のかたまりがあります。花軸の先は糸のように細長く仏炎包の外に伸びだします。(写真右下参照)果実は緑色をしており、花期は五~八月です。
つきあった雌花のかたまりがあります。花軸の先は糸のように細長く仏炎包の外に伸びだします。(写真右下参照)果実は緑色をしており、花期は五~八月です。和名のカラスビシャク(烏柄杓)は仏炎包の形が柄杓(ひしゃく)に似ているところからつけられました。塊茎は重要な生薬(しょうやく)で、外皮を除いて乾燥したものを半夏(はんげ)と呼び、痰(たん)を切り、吐き気を抑える作用があるので、各種の漢方薬に配合されます。
◆仏炎包(ぶつえんほう)は、サトイモ科の肉穂花序(にくすいかじょ)を包む包葉 例 ミズバショウ、ザゼンソウ
【写真左上、右下とも役場庁舎付近にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 コマツヨイグサはメマツヨイグサ(わしみやの野草77参照)と同じく北アメリカ原産の帰化植物で、明治末期から大正初期に日本に渡来したといわれています。急に多くなったのは昭和初期にはいってからで、現在では日本全土に広まっています。
コマツヨイグサはメマツヨイグサ(わしみやの野草77参照)と同じく北アメリカ原産の帰化植物で、明治末期から大正初期に日本に渡来したといわれています。急に多くなったのは昭和初期にはいってからで、現在では日本全土に広まっています。ふつう海岸の砂地や河原などに群生しますが、町内では道端の植え込みの中や舗装道路の歩道のすきまなどに生育しているのがみられます。メマツヨイグサは町内いたるところでみられますが、コマツヨイグサはここ数年のあいだにみられるようになった比較的新しい野草です。
茎は根ぎわから枝分かれして地表をはうか、斜めに立って高さ二十~六十センチになります。葉の形は、他のマツヨイグサとちがって、深く羽状に裂けたものから浅い波状の歯をもつものまであります。

花は葉のつけ根のところに一つずつつきます。ふつう六~八月の夕方に淡黄色の花を開き、がく片は下方に反り返ります。花の大きさは直径二~三センチで、翌朝にはしぼみ黄赤色に変わります。果実は二・五センチ前後で、種子は角ばらずなめらかです。
マツヨイグサ(待宵草)の名前は夕方に花が咲くのでつけられました。
【写真上左、下右とも鷲宮中学校近くの路傍にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 水田や池などの浅い水の中にはえる水草の一種です。生育場所が減少してあまりみられなくなりました。町内では、休耕田や稲刈りの終わった水田などでみられます。泥の中を地下茎が横にのび、節からひげ根を出します。茎は切り口が丸くてやわらかい毛がはえ、長さ十~三十センチ、ときには六十センチにもなります。茎の大部分は水面上にあって、細く切れ込んだ葉を五~八枚ずつ輪生(*)します。
水田や池などの浅い水の中にはえる水草の一種です。生育場所が減少してあまりみられなくなりました。町内では、休耕田や稲刈りの終わった水田などでみられます。泥の中を地下茎が横にのび、節からひげ根を出します。茎は切り口が丸くてやわらかい毛がはえ、長さ十~三十センチ、ときには六十センチにもなります。茎の大部分は水面上にあって、細く切れ込んだ葉を五~八枚ずつ輪生(*)します。水中の葉は水面上の葉よりも深い切り込みがあり、細く糸状で、これでも同じ種類かしら? と思うほど形に違いがあります。キクモやタチモ(ア
 リノトウグサ科)などの葉は、葉が水中にあるか空気中にあるかによって形が自在に変わることが出来ます。これは増水や渇水によって水位が変動する水辺に生育する水草の特性です。
リノトウグサ科)などの葉は、葉が水中にあるか空気中にあるかによって形が自在に変わることが出来ます。これは増水や渇水によって水位が変動する水辺に生育する水草の特性です。花期は八~十月で、水面上の葉の付け根に小さな紅紫色の唇形の花をつけます。花も果実も柄はほとんどありません。水中の葉にはしばしば閉鎖花(*)が出来ます。和名のキクモは葉が菊の葉に似ているのでつけられました。
※輪生…葉の着きかたの一つで、一節に三枚以上の葉が出ること。
※閉鎖花…開花することなく、自家受粉により結実する花で、花弁を欠くものが多い。
【写真左は上川崎地区、写真右は八甫地区の休耕田にて撮影】 写真と文 長須 房次郎