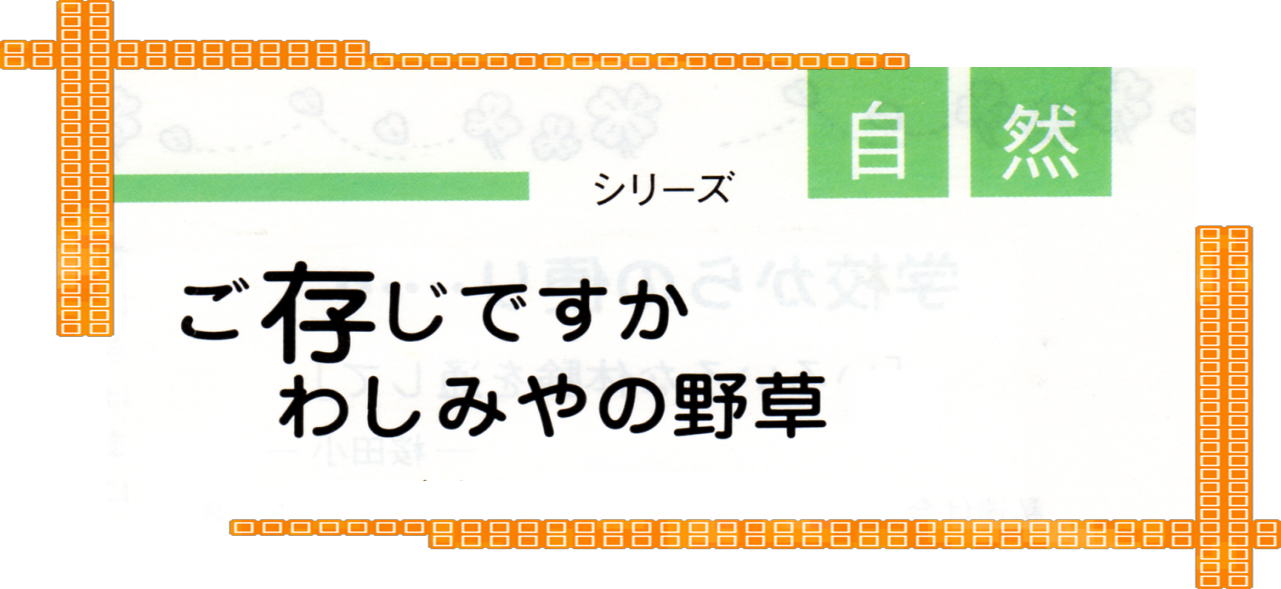
広報わしみや No.351~356
平成11年10月~平成12年3月
 チカラシバの名は「力芝」です。丈夫な根がしっかりと張り、引っばっても抜けないのでその名があります。チカラシバは、踏みつけに強いので農道や道ばたにカゼクサとともに列をなして生育します。
チカラシバの名は「力芝」です。丈夫な根がしっかりと張り、引っばっても抜けないのでその名があります。チカラシバは、踏みつけに強いので農道や道ばたにカゼクサとともに列をなして生育します。大きな株になって生え、葉は大部分が根元に集まっています。
茎の高さは三十~八十センチで、頂上に瓶を洗うブラシのような円柱形の花穂をつけます。
花期は八~十月で、花穂の直径は約二センチ、長さは十~十五センチあります。(右下写真参照)
子供のころ、道の両側に生えているカゼクサやチカラシバ
 を結び、後から来る人の足をひっかけて遊んだ経験がある人も多いと思います。これはもともと、「この草の強さに縁結びの願いを託したことに始まり、旅の安全祈願、道しるべの意味があった」 といわれます。
を結び、後から来る人の足をひっかけて遊んだ経験がある人も多いと思います。これはもともと、「この草の強さに縁結びの願いを託したことに始まり、旅の安全祈願、道しるべの意味があった」 といわれます。花穂の剛毛はふつう黒紫色ですが、淡緑色のものはアオチカラシバ、濃い赤色のものはベニチカラシバと呼ばれます。晩秋、草むらを歩くとチカラシバの実が衣服にたくさん付きますが、剛毛は種子の散布に役だっています。
【写真は左上、右下とも上内地内で撮影】
写真と文 長須 房次郎
 タウコギは、昨年刊行された 『埼玉県植物誌』 には、「水田の畦(あぜ)や湿地、溝などに生えるが、近年、数は極めて少なくなった」 と書かれています。
タウコギは、昨年刊行された 『埼玉県植物誌』 には、「水田の畦(あぜ)や湿地、溝などに生えるが、近年、数は極めて少なくなった」 と書かれています。かつては、水田や畦の雑草としてはびこつていましたが、大正時代に侵入したアメリカセンダングサ (北アメリカ原産) に追われ、さらに、戦後は農薬の影響で減少し大変少なくなりました。現在では、鷲宮町でも休耕田などの湿地にわずかに見られる程度になりました。
茎は無毛で切り口が円形なので、切り口が四角形のアメリカセンダングサやセンダングサと見分けられます。
花期は八~十月で、頭花は径一センチ内外、写真のように黄色で舌状花はなく、総包は大き
 く小さな葉のようにみえます。果実には、ふちと中央のすじの上と二本ののぎに下向きの棘(とげ)があり、動物の体に付いて運ばれます。
く小さな葉のようにみえます。果実には、ふちと中央のすじの上と二本ののぎに下向きの棘(とげ)があり、動物の体に付いて運ばれます。文献には、「中国では全草を気管支炎や肺結核に、茎や根を下痢止めに利用する」 と記されています。また、若葉は食用になります。
*ウコギはウコギ科の落葉低木、枝に棘(とげ)があり生け垣などに栽培される。
【写真は左上は宝泉寺池付近、右下は久本寺地内で撮影】 写真と文 長須 房次郎
 キクイモは北アメリカ原産の帰化植物で、イヌキクイモ (北アメリカ原産) はキクイモの一型との考え方もあ
キクイモは北アメリカ原産の帰化植物で、イヌキクイモ (北アメリカ原産) はキクイモの一型との考え方もあり、両者ともよく似ていて、ちょっと見ただけでは区別がつきません。
キクイモは、こぶの大きな塊茎(かいけい)(ジャガイモのように貯蔵物質を含むために地下茎がふくらんだもの)を作りますが、イヌキクイモは右下写真のように紡錘形(ぼうすいけい)の塊茎(かいけい)を作ります。牧野富太郎博士は植物研究雑誌(一九二六年)に、キクイモは幕末のころ英国の全権公使アールコックが高輪東禅寺内で栽培し、いもを自ら調理して安藤対馬守に試食させたという津田仙の記事を紹介しています。キクイモは近年食用としても美味な改良品種もできていますが、普通は豚などの飼料にされています。

イヌキクイモは黄色い径八センチ前後の頭花が咲き、荒れ地や道端、河畔などに生(は)えます。茎や葉はざらつき茎の上・中部の葉は互生で、下部は対生、総包片は二列が普通で、たまには三列のものもあります。塊茎が「ちょろぎ」に似ているのでチョロギイモともいわれます。
花期は普通七~十月ですが今年は暖かいので十二月はじめころまで見られそうです。
【写真は左上、右下とも西大輪の県道大宮~栗橋線の近くで撮影】 写真と文 長須 房次郎
 ウシハコベは春の七草の「はこべら」~ハコべ~ (わしみやの野草22参照)によく似ていますが、やや日陰の肥えた場所を好み、高さ六十センチぐらいになります。
ウシハコベは春の七草の「はこべら」~ハコべ~ (わしみやの野草22参照)によく似ていますが、やや日陰の肥えた場所を好み、高さ六十センチぐらいになります。茎は円柱形で暗紫色をしていて枝が多く、下部は地面をはい、先の方は斜めに立ち上がります。茎の下部の葉は葉柄(ようへい)が長く、上部の葉には葉柄はありません。茎やがく片に腺毛(せんもう)があり少し粘ります。
花弁は白色で五枚ですが、もとの方まで深く二つに分かれているので十枚あるようにみえます。また、めしべの先は五本に分かれています。ハコべのめしべの先は三本に分かれているのでこれがハコべと区別する決め手となります。(左上写真参照)

花期はふつう四~十月ですが、年間を通して花は見られます。ウシハコべもハコベと同様に利用することができます。ハコべに似ていて葉も花も大型なので、「牛はこべ」と名付けられました。
※腺毛(せんもう)…植物にある毛の一種で粘液などを分泌(ぶんぴつ)する。形は様々であるが、先端のふくれた棍棒状(こんぼうじょう)のものが最も多い。
【写真は左上、右下とも上内地区にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 東北地方南部以西に分布し、九州や四国にはシロバナタンポポ以外のタンポボが分布しない地域があり、そこでは 「タンポポの花は白い」 と思われているようです。他のタンポポとくらべ葉の緑がうすく、葉柄や葉脈がほとんど紫色をおびないなどの違いはありますが、花の咲く前にはなかなか区別できません。植物図鑑には花期は三~五月と記されていますが、実際には晩秋から初冬、一、二月にも開花します。(平成九年十二月十三目付け讀売新聞埼玉版)
東北地方南部以西に分布し、九州や四国にはシロバナタンポポ以外のタンポボが分布しない地域があり、そこでは 「タンポポの花は白い」 と思われているようです。他のタンポポとくらべ葉の緑がうすく、葉柄や葉脈がほとんど紫色をおびないなどの違いはありますが、花の咲く前にはなかなか区別できません。植物図鑑には花期は三~五月と記されていますが、実際には晩秋から初冬、一、二月にも開花します。(平成九年十二月十三目付け讀売新聞埼玉版)カントウタンポポは花粉が雌(め)しべについて受精(じゅせい)する両性生殖をしますが、シロバナタンポポはセイヨウタンポポと同じように受精をしないで種子を作ります。これは一種の単為生殖(たんいせいしょく)ですが、植物の場合は無融合生殖(むゆうごうせいしょく)と呼びます。(わしみやの野草⑬82参照)
「無融合生殖によってできる種子は 「母親」
 と同じ遺伝子をもつクローンのはず」 ~森田竜義氏が無融合生殖を行うシロバナタンポポの種子を調べたところ一〇〇個体以上がすべて同一クローン、つまり一株だったということです。日本中のシロバナタンボボが同一の可能性もあるのでは? もうそろそろ町内にもシロバナタンポボの花が見られると思います。探して見てください。
と同じ遺伝子をもつクローンのはず」 ~森田竜義氏が無融合生殖を行うシロバナタンポポの種子を調べたところ一〇〇個体以上がすべて同一クローン、つまり一株だったということです。日本中のシロバナタンボボが同一の可能性もあるのでは? もうそろそろ町内にもシロバナタンポボの花が見られると思います。探して見てください。【写真左上、右下とも中妻地内にて撮影】 写真と文 長須 房次郎
 野の草に醜草はなし犬ふぐり 稲畑 汀子
野の草に醜草はなし犬ふぐり 稲畑 汀子タチイヌノフグリはヨーロッパ原産の帰化植物で、明治のはじめ(一八八三年ごろ)東京に帰化し、いまでは全国にふつうにみられるようになりました。畑地や道ばた、あき地などに生育します。
茎は地ぎわで枝分かれして直立し、細い毛があります。葉はオオイヌノフグリ(わしみやの野草35参照)よりずっと小さく、下の方の葉は対生で大部分は柄がなく、両面とも短毛が生えています。上部の葉ほど小さくなって互生となり、包葉に移り変わり、それぞれ一個の花を抱き
 ます。花には柄がなく、花径は三~四ミリで、花期は三~六月です。
ます。花には柄がなく、花径は三~四ミリで、花期は三~六月です。似た種類のイヌノフグリやオオイヌノフグリは花にも果実にも柄がありますが、タチイヌノフグリには花にも果実にも柄がないので見分けられます。
在来種のイヌノフグリはオオイヌノフグリに押され、今ではほとんどみられなくなりました。俳句の世界ではオオイヌノフグリをイヌノフグリと詠んでいます。
【写真左上、右下とも八甫中川堤防にて撮影】
写真と文 長須 房次郎